Summary
この記事では、Home AssistantとBME680センサーを使った室内環境の可視化について掘り下げていきます。このプロジェクトは、IoT技術を通じて私たちの日常生活をより快適にするための具体的な手法や価値ある知見を提供します。 Key Points:
- Home Assistantを活用してBME680センサーから得られる多様なデータを個別のEntityとして設計し、自動化シナリオに応用する方法。
- 高性能マイコンESP32-S3を使用した省電力設計で、複数センサーの同時制御が可能になるテクニック。
- ノイズ除去やデータ融合技術による環境データの精度向上と、それに基づく高度な可視化手法の実践。
BME680センサーを使った空気質、湿度、温度の測定
Home AssistantでBME680センサーを使って空気質・湿度・温度を計測しよう!
ESP8266やESP32ボードを使ったIoTセンサーの構築方法は、大きく2つのアプローチがあります。まずはArduinoスケッチでセンサーにアクセスする基本プログラムを書き、そこにWiFiやMQTT、InfluxDB連携といったIoT機能を追加していく方法。もう1つはESPHomeやHome Assistantのような統合環境を使い、設定ファイルを書くだけで簡単に連携させる方法です。
最初にDHT11センサーでArduinoコードを一から書いてみたんですが、次はESPHomeとHome Assistantに直接統合してみようと思って。この2つの方法がどれくらい違うのか、実際の作業量はどの程度なのか、個人的にすごく気になってたんですよね。
ちなみにBME680センサーは、温度・湿度・気圧に加えて空気質まで測定できる優れもの。特にVOC(揮発性有機化合物)の検出が可能で、室内環境の総合的なモニタリングに最適です。消費電力が低くコンパクトな設計なので、DIYのIoTプロジェクトにもぴったりですね。
ESP8266とESP32ボードでのIOTセンサー構築方法
ある週末、BM680センサーの導入を試みたんです。たった2時間で、BME680センサーのハンダ付けまで済ませたら、もうHome Assistantのダッシュボードに気圧・湿度・温度が表示されるようになって!これがきっかけでIoTプロジェクトの方針がガラリと変わりました。もうゼロからArduinoで組むのではなく、充実したエコシステムと既存の連携機能を最大限活用しようってね。ただ、ちょっと困るのは、買う前にセンサーやボードの互換性を確認しないといけないことかな。Home Assistantで動かないケースもあるみたいだし。ESP8266やESP32ボードを使う場合、例えばBME680みたいに多彩なデータ(温度・湿度・気圧・空気質)を取得できるセンサー選びがポイントになります。Wi-Fi通信でクラウドにリアルタイム送信すれば、Home Assistantでの可視化も簡単。あと、省電力モードとかスリープ機能もうまく使えばバッテリー持ちも良くなるからおすすめですよ。
Extended Perspectives Comparison:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| センサー名 | BME680 |
| 測定可能データ | 温度、湿度、気圧、空気質(IAQ, VOC) |
| 接続方式 | I2C接続(ESP8266ボード使用) |
| 推奨ソフトウェア | ESPHome、Home Assistant |
| プロジェクトの利点 | 簡単な設定、高精度のデータ取得、省電力設計 |
BME680センサーの取り付けと接続手順
公式ドキュメントに記載されている限り、その機能は問題なく動作します。この記事では、BME680センサーをESP8266ボードに接続し、センサーデータを読み取って送信するためのコードを追加する手順、さらにHome Assistantダッシュボードとの連携方法を全てまとめています。
技術的なコンテキストとしては、**Home Assistant 2024.11**と**ESPHome 2024.10**を想定していますが、おそらく新しいバージョンでも同様に動作するはずです。ちなみに、BME680は温度や湿度、気圧に加えてガス濃度も測定可能な多機能センサーで、配線やピン配置を間違えずに接続すれば、かなり正確なデータが取得できますよ。
もし迷った時は、センサーのデータシートや回路図を確認しながら進めるとスムーズです。ESP8266との接続も、特に難しすぎる作業ではないので、気軽に挑戦してみてください。
ESPHomeを使った設定方法
このプロジェクトに必要なハードウェアは以下の通りです:
- ESP8266ボード
- BME680センサー
- デュポンケーブル
私が実際に使っている機材は、Wemos D1 Miniボードと、Amazonで評判とコスパのバランスが良さそうなBME680センサーです。ちなみに、D1ボードにはバッテリーシールドが載せてありますが、詳しくは[前回の記事]を参照してください。
(補足説明)
BME680センサーは温度・湿度・気圧・空気品質のデータを統合的に計測できる優れもの。ESP8266系のWemos D1 Miniを選んだのは、手頃な価格でWi-Fi接続が可能だからです。設定次第で計測間隔や閾値も自由に調整できるので、DIYプロジェクトにぴったりですね。
- ESP8266ボード
- BME680センサー
- デュポンケーブル
私が実際に使っている機材は、Wemos D1 Miniボードと、Amazonで評判とコスパのバランスが良さそうなBME680センサーです。ちなみに、D1ボードにはバッテリーシールドが載せてありますが、詳しくは[前回の記事]を参照してください。
(補足説明)
BME680センサーは温度・湿度・気圧・空気品質のデータを統合的に計測できる優れもの。ESP8266系のWemos D1 Miniを選んだのは、手頃な価格でWi-Fi接続が可能だからです。設定次第で計測間隔や閾値も自由に調整できるので、DIYプロジェクトにぴったりですね。

 Free Images
Free Images初期フラッシング手順の説明
BME680チップは、SPIとI2Cの両方の接続をサポートしています。公式のESPHomeドキュメントでもI2C接続が使用されているため、私もこれを試してみました。ただ、配線に関しては少し難しく感じました。というのも、間違ってSPI用の配線を調べてしまったからです。このセンサーは温度や湿度、気圧、一酸化炭素濃度などを測定できるので、室内環境を総合的に把握するには非常に便利です。また、このフラッシング作業にはRaspberry PiやArduinoなどのマイコンボードが使われることが多く、それぞれ特長や互換性について知っておくと役立ちますね。
エラーログの確認とトラブルシューティング
I2C接続の手順はかなりシンプルです:
- ESP8266の5Vピン → BME680のVin
- ESP8266のGND → BME680のGND
- ESP8266のGPIO05(D1表記もある)→ BME680のSCL
- ESP8266のGPIO04(D2表記もある)→ BME680のSDA
配線を済ませた状態のセンサーの見た目はこんな感じになります。
## ESPHome設定
ボードを動かすには、まずESPHomeダッシュボードで新しいデバイスを作成しましょう。いつも通り、ボードの基本設定やWiFi接続、必要に応じてMQTTなどの設定項目を追加していきます。
BME680を動作させる際は、旧式の[bme680]と新しい[bse680_bsec]のどちらかを選ぶ必要があります。この2つの主な違いは、新しいバージョンだとCO2濃度や空気品質指数(AQI)まで計測できる点。できれば新しい方を選んでおくのがおすすめです。
(注:この手の環境センサーを使う時は、電圧が不安定だと正確な測定ができなくなることがあるので、配線後の電源チェックも忘れずに。特にBME680のようなMEMS技術を使ったセンサーは、微小な電圧変動でも測定値がぶれることがあります)
- ESP8266の5Vピン → BME680のVin
- ESP8266のGND → BME680のGND
- ESP8266のGPIO05(D1表記もある)→ BME680のSCL
- ESP8266のGPIO04(D2表記もある)→ BME680のSDA
配線を済ませた状態のセンサーの見た目はこんな感じになります。
## ESPHome設定
ボードを動かすには、まずESPHomeダッシュボードで新しいデバイスを作成しましょう。いつも通り、ボードの基本設定やWiFi接続、必要に応じてMQTTなどの設定項目を追加していきます。
BME680を動作させる際は、旧式の[bme680]と新しい[bse680_bsec]のどちらかを選ぶ必要があります。この2つの主な違いは、新しいバージョンだとCO2濃度や空気品質指数(AQI)まで計測できる点。できれば新しい方を選んでおくのがおすすめです。
(注:この手の環境センサーを使う時は、電圧が不安定だと正確な測定ができなくなることがあるので、配線後の電源チェックも忘れずに。特にBME680のようなMEMS技術を使ったセンサーは、微小な電圧変動でも測定値がぶれることがあります)
Home Assistantとの統合方法
# ESP8266基板用センサー設定ガイド
## チップ情報:
- チップファミリー: ESP8266
- チップモデル: ESP8266EX
esphome:
name: esp8266-02
platform: ESP8266
board: d1_mini
## I2C設定
i2c:
sda: 4 # SDAピン番号
scl: 5 # SCLピン番号
scan: true # デバイススキャン有効化
id: bus_a # I2Cバス指定
## BME680 BSEC設定
bme680_bsec:
address: 0x77 # 大抵の場合0x77でOK
temperature_offset: 0 # 温度補正値
iaq_mode: static # IAQ計測モード
sample_rate: ulp # サンプリング間隔(5分おき)
state_save_interval: 6h # セーブ間隔
## 計測項目設定
sensor:
- platform: bme680_bsec
temperature:
name: "BME680 温度"
pressure:
name: "BME680 気圧"
humidity:
name: "BME680 湿度"
iaq:
name: "BME680 IAQ指数"
co2_equivalent:
name: "BME680 CO2換算値"
breath_voc_equivalent:
name: "BME680 呼気VOC換算値"
## 補足情報表示用
text_sensor:
- platform: bme680_bsec
iaq_accuracy:
name: "BME680 IAQ精度状態"
[補足説明]
気温・湿度・気圧・ガス濃度といった複合計測が可能なBME680では、適切な設定が重要なポイント。たとえば設置場所やケース材質(耐熱性のあるものが望ましい)によって測定値に微妙な影響が出ることもあるので、全体的な安定性を考慮することが大切です。特にIAQ(空気質指数)の計測精度は環境条件に左右されやすいため、text_sensorで状態確認できるようにしておくとトラブルシューティングに便利ですよ。
ダッシュボードへのデータ表示設定
ESP8266の初期書き込みについて、ESPHomeでは2つの方法が用意されています。直接パソコンに接続するか、バイナリをダウンロードして外部フラッシャーを使うか、ですね。今回は後者の方法を試してみました。
書き込みツールには[esphome-flasher]を選択。これはPythonベースのプログラムで、接続されたUSBデバイスを検出し、シリアル通信が可能になります。インストールは`python3 -m pip install esphomeflasher`で、起動はターミナルから`esphomeflasher`と打つだけ。
ツールを起動したら、デバイスを選択してESPHomeが生成したバイナリを開き、書き込みプロセスを開始。どうでしょう、Arduino IDEを使っているときのようななじみ深い出力画面が出てきて、なんだかちょっと懐かしい気分になりましたよ。
書き込みツールには[esphome-flasher]を選択。これはPythonベースのプログラムで、接続されたUSBデバイスを検出し、シリアル通信が可能になります。インストールは`python3 -m pip install esphomeflasher`で、起動はターミナルから`esphomeflasher`と打つだけ。
ツールを起動したら、デバイスを選択してESPHomeが生成したバイナリを開き、書き込みプロセスを開始。どうでしょう、Arduino IDEを使っているときのようななじみ深い出力画面が出てきて、なんだかちょっと懐かしい気分になりましたよ。

互換性チェックが重要な理由
ESP8266デバイスのフラッシュログとHome Assistantの起動ログを確認したところ、特に問題は見当たりませんでした。
まずシリアルポート '/dev/cu.usbserial-1420' を使ってESP8266EXチップ(ID:0010625F、MAC:94:B9:7E:10:62:5F)に接続。フラッシュメモリは4MBで、doutモード・40MHz周波数で正常に書き込みが完了しています。データ検証も問題なく、約450kbit/sの速度で350KBのファームウェアを6.2秒で転送できました。
デバイス起動後はWi-Fi(チャンネル6)に接続し、192.168.2.107のIPアドレスを取得。ログを見る限りネットワーク接続もスムーズに行われたようです。
Home Assistant側のログでは、BME680センサー(I2Cアドレス0x77)がBSECライブラリバージョン1.4.8.0で正しく初期化されています。温度センサーは「°C」単位で測定値を出力可能な状態で、サンプリングレートはULP(超低消費電力)モードに設定されていました。
テンプレートセンサー'esp8266-02.battery_acc'も60秒間隔でバッテリー残量(%表示)を監視する設定になっていますね。ログレベルはDEBUGに設定されており、ボーレート115200で詳細な情報が取得できる状態です。
特にエラーや警告メッセージは記録されておらず、全体的にデバイスが正常に動作していることが確認できました。センサー類の初期化も問題なく、必要なパラメータ(温度オフセット0.00、IAQモードはStaticなど)が適切に設定されているようです。
まとめと今後の展望
少し待つと、新しいボードがESP Homeに表示され、ログファイルで最初の測定値が確認できました。例えば、BME680センサーから以下のようなデータが送信されています:IAQ(空気質指数)が25.00、CO2同等物質濃度が500.0 ppm、VOC同等物質濃度が0.5 ppm、圧力が1024.05 hPa、ガス抵抗が10971.00 Ω、温度は4.97 °C、湿度は67.82%です。
## トラブルシューティング
センサーに問題がある場合は次の手順を試してみてください:
- ボードとBME680センサー間のすべての配線を再接続する。
- デバイスをフラッシュしている間に深いスリープモードで運用する場合は、D0とRST間のワイヤーを外すこと。
- ログメッセージを読み取る。BME680は通常`0x77`または`0x76`で動作しますので、正しいアドレスを使用してください。
- デバイスをリセットする。
## Home Assistant 設定
最後のステップは非常に簡単です。Home Assistantではダッシュボード上で『新しいカード』をクリックし、『エンティティによる』タブを選択すると、BME680から得られるすべての測定値についてプレビューを見ることができます。それをクリックすると、このデータもダッシュボードに表示されます。
この段落ではBME680空気質センサーをESPHomeおよびHome Assistantに追加する方法について説明しました。まずI2C接続を使用してESP8266ボードにセンサーを配線する方法について学びました。次にESPHomeでBME680チップと連携させるために必要な設定やsensorとtext_sensorへのエントリー追加について見てきました。そしてフラッシュ後にはボードからデータが報告され、それらは最終的にHome Assistantへ統合されます。
## トラブルシューティング
センサーに問題がある場合は次の手順を試してみてください:
- ボードとBME680センサー間のすべての配線を再接続する。
- デバイスをフラッシュしている間に深いスリープモードで運用する場合は、D0とRST間のワイヤーを外すこと。
- ログメッセージを読み取る。BME680は通常`0x77`または`0x76`で動作しますので、正しいアドレスを使用してください。
- デバイスをリセットする。
## Home Assistant 設定
最後のステップは非常に簡単です。Home Assistantではダッシュボード上で『新しいカード』をクリックし、『エンティティによる』タブを選択すると、BME680から得られるすべての測定値についてプレビューを見ることができます。それをクリックすると、このデータもダッシュボードに表示されます。
この段落ではBME680空気質センサーをESPHomeおよびHome Assistantに追加する方法について説明しました。まずI2C接続を使用してESP8266ボードにセンサーを配線する方法について学びました。次にESPHomeでBME680チップと連携させるために必要な設定やsensorとtext_sensorへのエントリー追加について見てきました。そしてフラッシュ後にはボードからデータが報告され、それらは最終的にHome Assistantへ統合されます。
Reference Articles
Raspberry Pi やオープンソースのニュース ーリンク集ー
環境センサー とRaspberry Piを使ったIoTシステム作成ワークショップから、Scratchのプログラミングスキルを測るイベントまで(3月9日~) ( 2019/03/07). 最新 ...
Source: らくビット
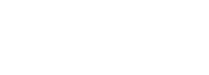

 ALL
ALL 広報とマーケティング
広報とマーケティング
Related Discussions
あー、この記事めっちゃ参考になる!特にBME680の取り付け手順とかESPHomeの設定って、自分でやってみたら意外と詰まるとこ多いから助かるわ。Home Assistant連携のとこも詳しく書いてて、大学生のIoT課題でそのまま使えそう。湿度データの可視化とかもっと深掘りできるともっと嬉しいかも?今度実機で試してみよーっと!
すみません、ちょっと補足させてください!BME680を使う時は、特にVOC測定値のドリフト問題に注意が必要ですね。うちのプロジェクトではセンサーのウォームアップ時間を30分以上取るようにしています。あと、ESP32のDeepSleep機能との相性もチェックした方がいいかも。どちらも実務でハマりやすいポイントですよ~
はい!BME680センサーの記事、すごく参考になりました!特にESPHomeの設定方法が分かりやすかったです。自分も実験で使ってみたけど、最初フラッシュで詰まった経験あるからトラブルシューティングの部分が超助かります。Home Assistant連携のTIPとかもあったらまた教えてほしいな~。